Why gun violence can’t be our new normal | Dan Gross


Why gun violence can’t be our new normal | Dan Gross

Heated debate on gun control
Celebrities DESTROY Whoopi Goldberg And The View Panelists On Gun Control
A Gun Regulation Analogy For All You Stoners
Hillary Clinton Supports Australia-style Gun Confiscation
H.R. 3999 Gun Control Legislation
Awesome Gun Control Debate (15:26)
Debunking Gun Control Arguments
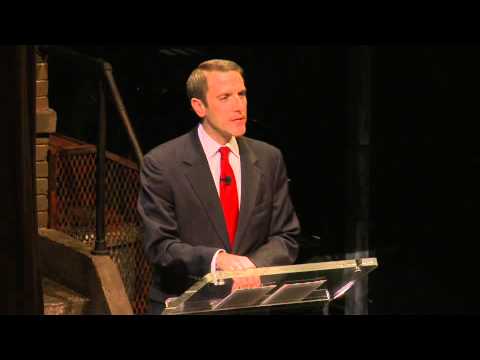
英検1級受験対策:トピック「税金を使って芸術活動を支援すべきか?」
Public Support of the Arts: Seth Pinsky at TEDxBroadway
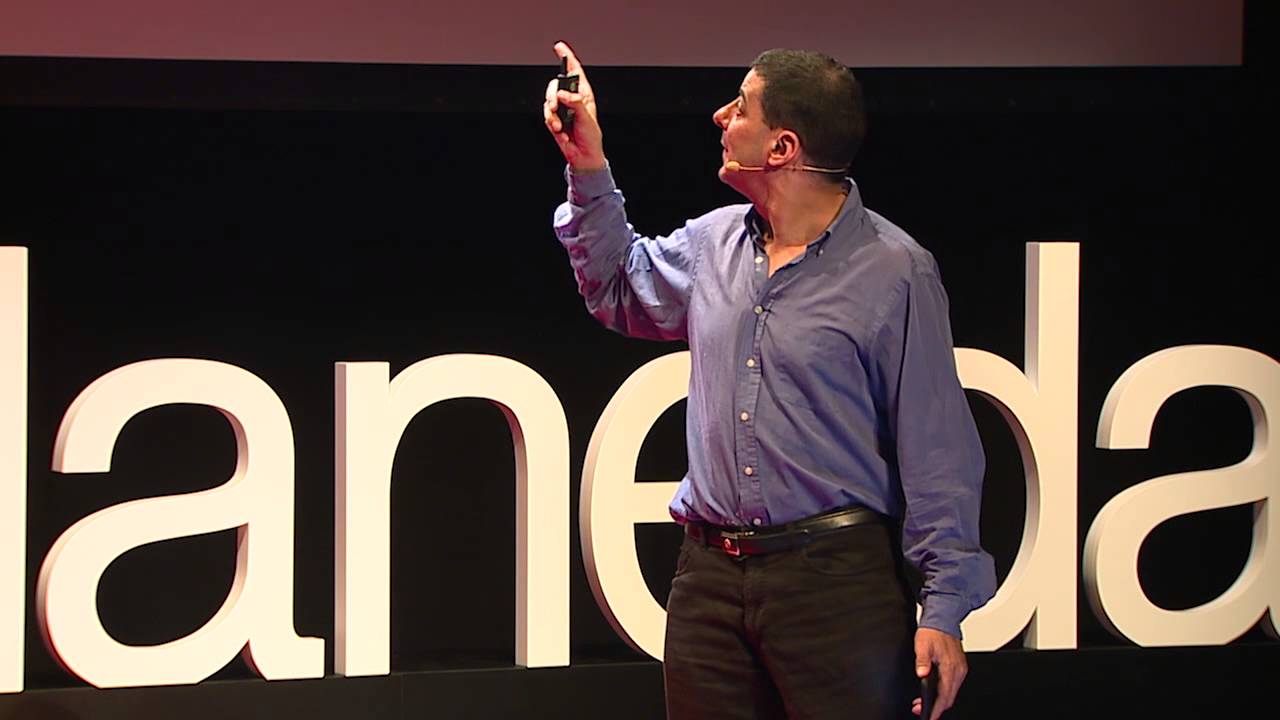
日本におけるジャーナリズムの危機について、ジェイク・エーデルスタイン(Jake Adelstein)が語るTED。
In search of truth – Truth, as seen by an American journalist | Jake Adelstein | TEDxHaneda
The New Censorship Joel Simon talked about his book, The New Censorship: Inside the Global Battle for Media Freedom, in which he examines the targeting of journalists by governments around the world, including the U.S. government.
https://www.c-span.org/video/?322577-1/book-discussion-new-censorship (1:00:34)
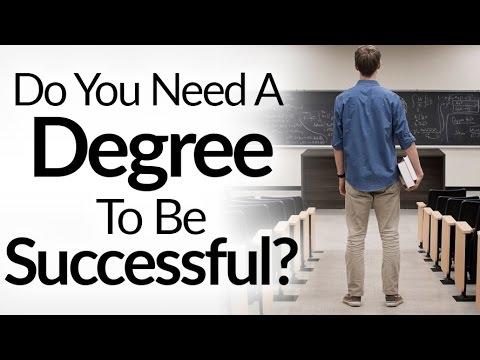
英検1級対策。「大学の学位は人生の成功にとって必要か」
小学生は自由な発想をまだ持っているのに、中学、高校と教育を受けることで画一的にしかものを考えられない人間になってしまう、と鋭く学校教育を批判。
How School Makes Kids Less Intelligent | Eddy Zhong | TEDxYouth@BeaconStreet
大学の学位は人生の成功にとって必要かどうかに関して、否定的な論陣を張っている動画。
The Most Successful People Explain Why a College Degree is USELESS
Do You Need a Degree To Succeed? | 5 Reasons College Does NOT Equal Success | University Myths

The Professors 709 – Status of Science Education in America
英検1級で過去に出題されたトピックに関する動画を見て、受験対策を練りましょう。
動画 It’s too late to do anything about climate change…. right? https://www.youtube.com/watch?v=bv7zFAdZ6LI 7:55 では、気象学者が意見を述べていて、非常に英語表現の勉強に使えます。文例を紹介します。
Climate Change 101 with Bill Nye | National Geographic https://www.youtube.com/watch?v=EtW2rrLHs08 4分9秒
強調構文の公式は、強調したいものを It is …. that と挟むことです。ある文が強調構文かどうかは、It is と that を取り除いたときに完全な文が残るかどうかで判別できます。完全な文があれば、強調構文。
It wasn’t the White House, it wasn’t the State Department, it wasn’t father LaVar’s so-called people on the ground in China that got his son out of a long term prison sentence – IT WAS ME. Too bad! LaVar is just a poor man’s version of Don King, but without the hair. Just think..
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年11月22日
彼の息子を牢獄から出してやったのは、俺だ!と強調構文を使っています。やや変則的ですが、
The White House got his son out of a long term prison sentence.がもとの文として、主語を強調すると
It was the White House that got his son out of a long term prison sentence. となります。このツイートではそれがさらに否定形になっているだけです。同様に、
Trump got his son out of a long term prison sentence. が元の文と考えると、理解できるでしょう。これの文でTrumpを強調するために,It was … thatではさみこむと、
It was Trump that got his son out of a long term prison sentence. という強調構文が出来上がります。Trump本人の言葉なので、Trumpの部分が、Iとなるわけですが、実際には語呂の問題なのかmeになります。Iじゃなくてmeになるのは例外的な変化と考えらるでしょう。
マーティン・ファクラー著 「本当のこと」を伝えない日本の新聞 に、新聞で発言のソースを示す言い方がいくつか紹介されていました。マーティン・ファクラー氏はニューヨークタイムズの記者で、日本に長くいて日本の情報を世界に発信しています。
said one American official, who asked tnot to be named. 名前を明かせないというアメリカ政府の職員はこう言った
a State Department official 国務省職員
American official アメリカ政府の職員
someone close to the matter この問題に詳しい人物;消息筋
(参照部分:112~113ページ)
現行のセンター試験は廃止され、2020年から新しい試験制度が導入されます。とくに大きく変わる科目が英語です。長文読解に偏重していた英語教育から、読む、書く、聴く、話すの4技能をバランス良く教育し、大学入試においてはその能力を測るという方向に改革が行われます。センター試験に変えてマークシート式でなく民間の試験制度を利用するというのが一番大きな変化でしょう。今(2017年11月3日)の時点では、どの試験が採用されるのかは決まっていません。新聞報道では、英検、TOEFL、などが挙げられていますが、まったく不透明な状態です。受験生にしてみれば、たまったものではありませんね。
しかし、どの民間試験が採用されようとも、確かな英語力、4技能を身につければいいだけの話です。読む、聴くはいいとして、書く、話すはどうやってスキルを身につければいいのでしょうか?だいたい、英語で書く、英語を話すということを教育できる先生は今の日本にはほとんどいないのではないかと思われます。公立高校でも英語の授業を英語で行っている先生がいるようですが、どれくらい効果があるのかは疑問です。
文科省の資料によれば、民間試験として「例」として挙げられているのが、
の7つです。TOEICはビジネス英語なので、大学入試にはそぐわないと思いますが、実際のところ何が選ばれるのか、わかりません。英検は中学や高校で受けさせるところが多いので、一番スムーズに導入できそうな気がします。TOEFLは海外の大学に留学するときに必須の試験ですので、これも大学入試として用いるのは非常にリーズナブルでしょう。