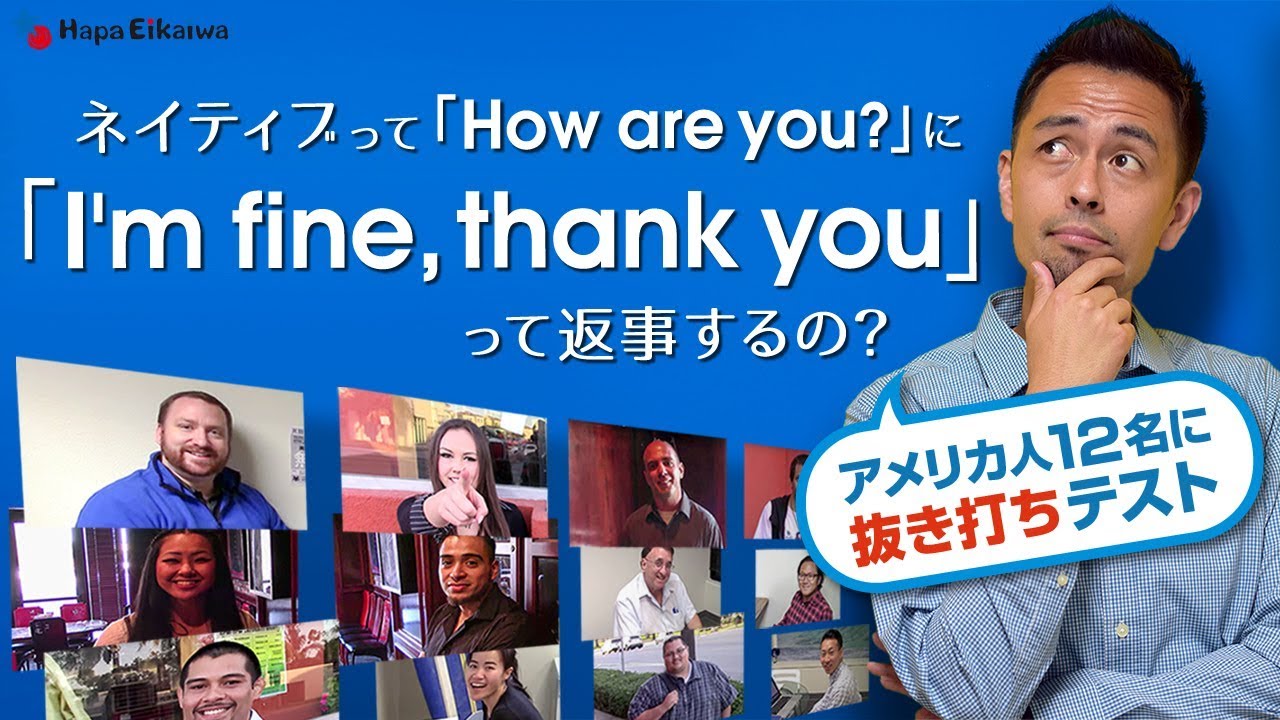予備校の解答には間違いがあることもあるということで、上智大学外国語学部2017年の問題、大問8の中の問題を紹介します。
(68) According to Paragraph 2, what makes The Leaf the first of its kind?
(a) It is an all-electric car.
(b) It is made in the United States.
(c) It is available for anyone to buy.
(d) Its battery never needs charging.
この問題に答えるために第2パラグラフの該当箇所をみてみますと、第1文に
The Nissan Leaf is the world’s first all-electric car to be produced for the mass market in the United States.
とあります。日産リーフが電気自動車だということは多くの人は広告などからご存じでしょう。そうすると簡単に答えは(a)だということがわかります。ところが、東進の解答を見てみると(c)になっているんですね。パスナビを見てみると(a)が答えです。予備校によって解答が割れるということはまあ必ずしも珍しいことではありません。しかし、生徒にしてみるとどっちを信用すればいいの?ということになって困ります。
of its kind のkindの内容に該当する部分を和訳すると、「アメリカ国内で大衆向けに生産された世界初の全電気自動車」となるわけですが、選択肢(d)は事実ではないので却下するとして、他の選択肢を和訳すれば、
(a)全電気自動車、
(b)アメリカ国内で生産された、
(c)大衆向け
となり、これらの選択肢に書かれている「情報」は確かにどれも、この本文の和訳した部分に、部分的に含まれています。となると、its kindはいったいどんな種類の車の話なの?ということになります。
初めての全電気自動車なのか?
初めてアメリカで生産された車なのか?
初めて大衆が買えるようになった車なのか?
と考えれば、この文章が全電気自動車について書かれた内容であることは明らかなので、「全電気自動車」として最初ということになり、答えは(a)とわかります。(c)の大衆向けの最初の車と聞くと、T型フォードが思い浮かびます。